2024年7月14日 反省。
ネットロアの巨頭オのイラストを描いてみた。でも、正直、あんまりうまく描けなかった。気持ち悪くなってしまった。まあ、気持ち悪いのが「妖怪」ではあるんだけど、そういう気持ちの悪さではなくて、据わりの悪さみたいなのがある。うーん。アップしなければよかったか。まあ、pixivとXに投稿してしまったので、このまま前に進んでいこう。
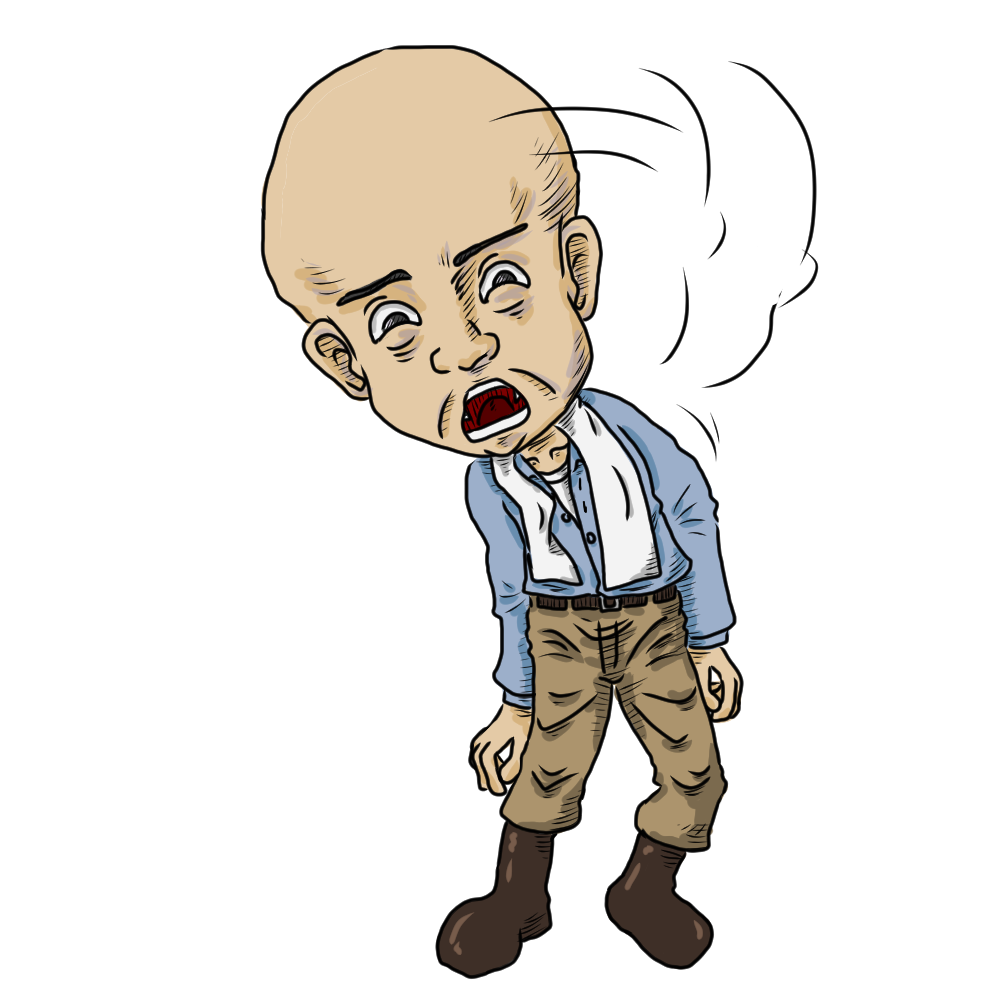
実は、ボクはイラストに関しては、数週間先まで予定を組んで、締め切りを設けながら描いている。自堕落なので、そうしないと続けられないと思っているからだ。そして、ちょっと仕事に忙殺されて、締め切りが押せ押せになっていたので、えいや、で描いて投稿してしまった。
巨頭オが服を着ているのか着ていないのかは議論が分かれるところだ。結構、裸ん坊の巨頭オのイラストを多く見かける。でも、ボクは巨頭オは服を着ているんじゃないかと思っている派だ。何故なら、目撃者が巨頭オのことを、頭の大きい「人間」と認識しているからだ。二足歩行の獣でも、サルでもなくって、人間と認識しているから、一程度の文化は持っているのではないかと想像する。また、「巨頭オ」という看板をつくるわけだから、これも文化のある証拠だ。ましてや「巨頭村」だったのであれば、尚更、村としての自治はあるはずだと思っている。そんなわけで、服を着せてみたんだけど、ちょっとそれが悪さをしたかな、と思っている。農業をやっている雰囲気を出したくて、タオルを巻いたのが、変に生っぽくなってしまった。もっとシンプルな個性のない服装にすればよかったかもしれない。反省しきりである。
2024年7月5日 インターネットで広まった怪異が検索しても出てこないのはなぁぜ?
インターネットが登場して、どのジャンルにおいてもプロとアマの区別が曖昧になった。誰もが情報発信できる時代になって、必ずしも大手の後ろ支えがなくっても活躍できる。クリエイターにとっては喜ばしいことだと思う。
同じような流れが「都市伝説」のジャンルでも起こっている。昔は、誰かが語った「怪異」は、雑誌や本に載ることである程度、箔がついた。誰もが勝手に「怪異」を語ることはできても、それで終わってしまう。それを追認するプロセスを経て、一般に膾炙した。でも、今はオカルト掲示板などに投稿して、それなりの評価がなされれば、あっという間に「都市伝説」の仲間入りをしてしまうし、「現代妖怪」の仲間入りをしてしまう。本来、都市伝説というのは、多くの人たちが信じてこそだった。今はネタとして投稿され、ネタとして消化され、それが「都市伝説」的な整理で本やウェブサイトで紹介される。結果として、都市伝説の敷居がものすごく低くなってしまった気がする。
データベースを扱う人間は、メジャーなものは当然として、マイナーなものを蒐集して紹介したくなる。ウェブサイト「ファンタジィ事典」を編纂しているボクだってそうだ。非常にマイナーなものにこそ、情報の価値がある。でも、そうなると、オカルト板の端っこで語られている「怪異」を「こんな怪異があるよー」って紹介したくなる。「こんな現代妖怪がいるよー」って紹介したくなる。一旦、本や雑誌、まとめサイトに紹介されると、メジャーな都市伝説もマイナーな都市伝説も横並びだ。さも有名な「怪異」のようになってしまう。
今、都市伝説関連の書籍には、インターネットで語られるいろんな都市伝説(ネットロアという呼び方もあるけれど)が玉石混交、紹介されている。読者の人には、一度、インターネットで調べ直して欲しいなと思う。「〇〇年頃にインターネットで広まったもので……」みたいに実しやかに書いてある。でも、検索しても、まったくヒットしないものも多い。あるいは検索しても、本当に数件しかヒットしないものもある。それって、インターネットで語られる都市伝説なのだろうか。まあ、「インターネットで広まった」という言説そのものが事実ではないということも含めて都市伝説っぽさはあるので、それはそれで面白いんだけど、でも、ライトな読者には、どの程度の知名度で語られている怪異なのかは、全く判断できない。
クリエイターにとって、プロとアマの垣根がなくなるのはよいことだ。純粋に作品の良さで勝負できるようになった。都市伝説も同じであればよいと思う。でも、必ずしもそうではない現状がある。
2024年4月24日 ネットロアは都市伝説なのかネタなのか。
最近、朝里樹氏が精力的に都市伝説の本を出している。ボクは比較的、都市伝説も視野に入れて情報収集している方だが、結構、知らないものもたくさん載っている。最近の都市伝説はネットロアが多い。昔だったら、学校や学習塾が都市伝説の媒介になっていた。ときには雑誌やラジオというメディアが介入して、日本各地に広がっていった。今はインターネットの時代なので、当然、インターネット上で拡散していく。匿名の誰かが書き込んだ物語があっちこっちにコピペされながら、コメントがつけられながら、拡散していく。その拡散の速さは口伝えとは比にならない。そして、たくさんの都市伝説が量産されて消費されていく。
都市伝説の量産と消費が、ボクは少しだけ気になっている。昔は「トイレの花子さん」とか「口裂け女」、「人面犬」など、子供たちの間で爆発的に拡散していったとは言え、口伝えだから、広がり方には限界があるし、ムラがある。話には尾ひれがついて変容していく。でも、ネットロアではログが残る。いつ、どこで、どのように語られたのか、最初の書き込みを辿ることができる。だから、みんなで少しずつ都市伝説をつくっていくというよりは、特定の「作者」の存在が透けて見える。ネタのように投稿して、バズっていく感覚がある。
だから、最近の都市伝説と呼ばれるものは物語の展開が複雑で、創作性が高い。ある意味ではよく出来ている。そういう匿名の誰かの創作物を、都市伝説の解説サイトや解説本で紹介することで、あっという間に都市伝説だと認定されてしまう。でも、本当にそれって都市伝説なのだろうか。創作ホラーとか、ネタの一種で、お遊びではないのか。書き手も読み手も、エンタメとして楽しんでいるだけで、リアリティを感じて怖がっているのかどうか定かではない。
山口敏太郎氏の本は、そういう意味で、何でもありという感覚があった。最近の朝里氏も、有名なものを紹介し尽くして、マニアックなものを紹介し出して、少しだけ、その方向性を感じている。ボクも「ファンタジィ事典」を運営しているので、そういう意味では、同じ穴のムジナなので、気を引き締めなきゃいけない。まあ、ボクもごった煮な感じで、混然一体とはしているのだけれど……。




